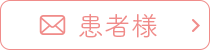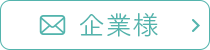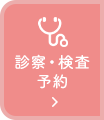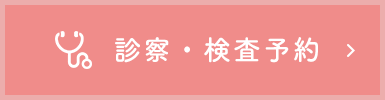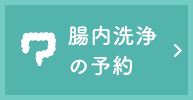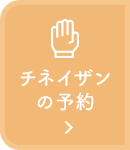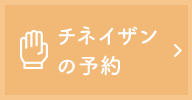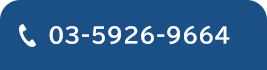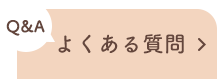脂肪肝と睡眠時無呼吸症候群(SAS)の関係とは?
脂肪肝(MASLDやMASH)と睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)は、一見無関係のように思えますが、近年、これらが密接に関連していることが分かってきました。特に、どちらの疾患も肥満や生活習慣病と深く関わりがあり、互いに悪影響を及ぼすことがあるため、同時に管理することが重要です。
東長崎駅前内科クリニックではそれぞれの疾患を同時に診断治療ができるクリニックです。
本記事では、脂肪肝とSASの関連性、症状、検査、そして治療法について詳しく解説します。池袋、豊島区エリアにお住まいの方で、これらの疾患に心当たりのある方はぜひ参考にしてください。
・脂肪肝と睡眠時無呼吸症候群(SAS)の関係
1. SASが脂肪肝を悪化させるメカニズム
SASでは、睡眠中に繰り返される低酸素状態が肝臓に炎症を起こします。
- 低酸素血症が肝細胞にストレスを与え、肝臓内での炎症を促進します。
- 繰り返される炎症反応や酸化ストレスを引き起こし、脂肪肝の進行(MASHや肝線維化)に寄与します。
2. 脂肪肝がSASを悪化させる影響
脂肪肝に伴う肥満や内臓脂肪の蓄積は、気道を狭くし、SASの発症リスクを高めます。
- 肥満が気道の周囲に脂肪を蓄積させ、気道閉塞を引き起こします。
- 肝臓での炎症や代謝異常が、全身の炎症を増幅させ、SASの重症化につながる可能性があります。
・SASと脂肪肝のリスク要因
以下のリスク要因を持つ方は、SASと脂肪肝の合併に注意が必要です。
- 肥満:BMIが高いほどリスクが上昇。
- 中年以降:40歳以上で発症率が高まります。
- 生活習慣病:糖尿病、高血圧、脂質異常症が両疾患の共通リスク。
- アルコール:過剰摂取が肝臓と睡眠の両方に悪影響を及ぼします。
・症状のサインに注目
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状
- 睡眠中のいびきや呼吸停止
- 日中の眠気や疲労感
- 起床時の頭痛や喉の渇き
- 集中力や記憶力の低下
脂肪肝の症状
- 初期段階では無症状であることが多い
- 進行すると、倦怠感や腹部の違和感が現れる場合も
- 肝機能検査でAST/ALT値の異常が確認される
・脂肪肝とSASの検査方法
1. 脂肪肝の検査
- 血液検査:肝機能(AST/ALT/γ-GTP)や脂質代謝(中性脂肪、LDL/HDL)を評価
- 超音波検査(エコー):肝臓の脂肪蓄積を可視化
- 肝線維化スキャン(FibroScan):線維化や進行度の評価
2. SASの検査
- 簡易睡眠検査:睡眠中の酸素飽和度や呼吸パターンをモニタリング
- ポリソムノグラフィー(PSG):専門施設で行う詳細な睡眠検査でしたが近年では自宅でも検査可能です。
- 肥満度評価:BMIや腹囲を測定
・脂肪肝とSASの治療方法
1. 生活習慣の改善
- 食事療法:カロリー制限、糖質・脂質のコントロール
- 運動療法:有酸素運動と筋力トレーニングを週3~5回
2. SASの治療
- CPAP療法(持続陽圧呼吸療法):睡眠中の気道閉塞を防ぐデバイス
- 体重管理:減量によりSASの重症度が軽減
3. 脂肪肝の治療
- 糖尿病や脂質異常症の治療:血糖値や脂質のコントロール
- 新規治療薬の適応:進行度に応じた薬物療法
・池袋、豊島区周辺で脂肪肝とSASの診療を同時に受けるには?
東長崎駅前内科クリニックでは、脂肪肝とSASの検査や治療が可能です。
当院では睡眠時無呼吸症候群の検査として自宅でできるポリソムノグラフィー(PSG)が可能です。
また脂肪肝やそのほかの生活習慣病も同時に治療可能なので、当院で全体の管理ができます。
今まで睡眠時無呼吸症候群と他の疾患を別医療機関で通院していた方は当院ですべて管理できます
これらの疾患は早期発見と管理が重要です。特に肥満や生活習慣病の既往がある方は、専門医の診察を受けて、適切な治療計画を立てましょう。
脂肪肝とSASを放置すると、全身の健康に深刻な影響を与えるリスクがあります。健康的な生活を送るために、早めの行動が大切です。
脂肪肝専門外来(アルコール性脂肪肝、非アルコール性脂肪性疾患/NAFLD、非アルコール性脂肪性肝炎/NASH)