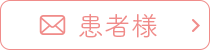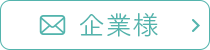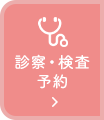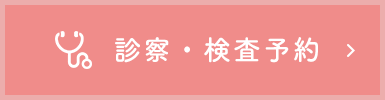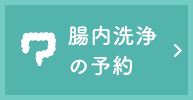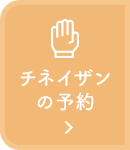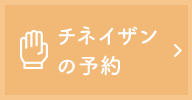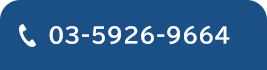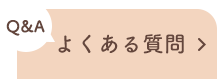こんにちは😊
9月に入りましたが、まだ厳しい残暑が続いております。
みなさんはいかがお過ごしでしょうか?
今回は肝臓の病気である肝炎・肝硬変についてお話しさせていただきます。
【慢性肝炎】
慢性肝炎とは主にB型、C型などの肝炎ウイルスの感染によって、肝臓の炎症が6ヶ月以上続くものをいいます。
・C型肝炎ウイルス(HCV)・・・輸血や血液を介した接触で感染
・B型肝炎ウイルス(HBV)・・・輸血、性行為、出産時の母子感染などで感染
この他にもアルコールの過剰摂取や薬剤によるものもあります。
自覚症状は無いことがほとんどですが、場合によっては全身倦怠感、食欲不振などがみられることがあります。
治療の基本は肝硬変へと移行させないことであり、抗ウイルス薬を用いた薬物療法などがあげられます。
【NAFLD・NASH】
アルコールを過剰摂取してない状況で生じた脂肪肝の状態を非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)といいます。
こちらは糖尿病、脂質異常症、肥満、高血圧などに関連して発症することがほとんどです。
またNAFLDの重症型を非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)といい、肝硬変や肝癌に進行することがあります。
治療としては運動や食事療法による生活習慣の改善、薬物療法があります。

【肝硬変】
肝硬変とは長期間にわたって炎症によるダメージを受けた結果、肝臓が硬くなり機能が低下した状態をいいます。
肝硬変は代償期と非代償期の2つの段階にわけられます。
・代償期
肝硬変の初期段階で肝臓がまだ一定の機能を維持している状態です。
自覚症状はほとんどみられません。
・非代償期
肝硬変の進行により肝臓の機能が維持できなくなった状態に陥った状態です。
非代償期では全身倦怠感、食欲不振、手足のむくみ、皮膚瘙痒感などの自覚症状がみられます。
ほかにも黄疸、腹水、肝性脳症などの症状もみられることがあります。
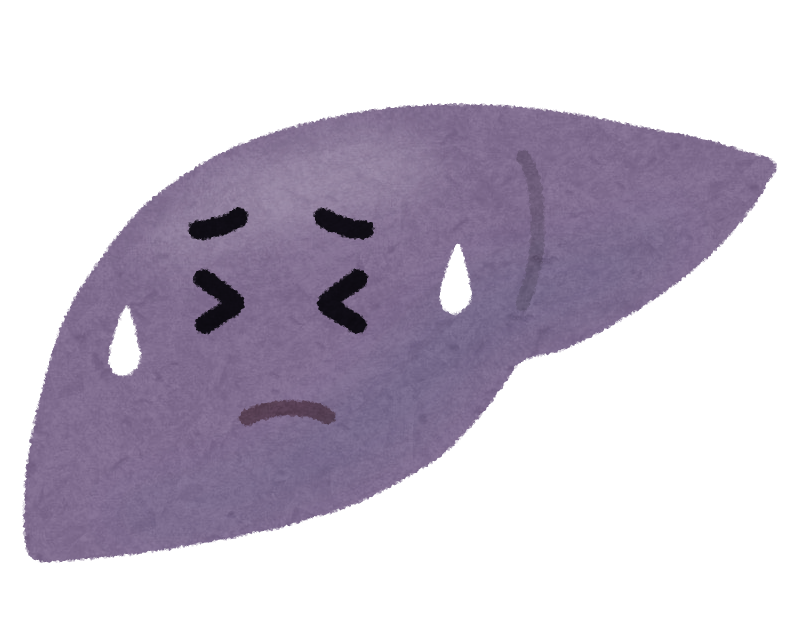
肝硬変の治療は症状や進行度によって異なります。
アルコールやウイルス感染による場合はその原因の是正、治療を行います。
合併症が起きた場合はその症状に応じた治療法を選択します。
また肝硬変では糖の利用能力の低下などにより栄養不良が起こりやすいため、肝硬変の進行を止めるためにも栄養療法は重要になります。
次回は肝炎・肝硬変の具体的な食事療法についてお伝えします。
当院では管理栄養士による栄養指導を実施しております。
気になる方はぜひお気軽にスタッフまでお声がけください。
ウイルス性肝炎についてはこちら
慢性肝障害についてさらに詳しくはこちら
超音波検査・フィブロスキャン検査についてはこちら
外来の予約はこちら
【管理栄養士による栄養指導】
・日時
月16:00
水16:00
木11:00、16:00
金16:00
土10:00、11:00
・所要時間
初回30分、2回目以降20分
・料金(保険3割負担の方)
初回780円
2回目以降600円
・予約方法
受付や医師にお声がけ下さい
今後はWEB予約もできるようにしていきます。
※医師の診察を受けていただき、指導の指示のある方が対象となります。